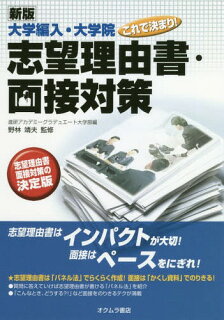大学編入の面接って何を聞かれるんだろう?
何をどう対策すれば良いのか分からない。
これまで面接をした経験が少ないから不安。
上記のような疑問・不安を抱えている方に向けて、今回は大学編入の面接対策法について解説します。
ここで紹介する方法は、ただの筆者の経験談という訳でもなく、編入コースで有名な学校でも行われている方法になります。編入面接を控えている方々は是非参考にしてください。
※筆者の編入経験についてはこちらを。編入面接の経験は3回。(関大2回、同志社1回)
偏差値40のバカが専門学校を経て『関関同立』に編入・卒業した話。【経験談】
記事の詳細は目次をチェック↓↓↓↓
スポンサーリンク
編入面接での頻出質問

- 大学・学部の志望理由。
- 大学卒業後の進路。
- 大学で研究したいこと。
- どの教授のゼミで研究したいのか。
- 最近、読んだ本は。
- これまでの学生生活で頑張ったこと。
筆者が受験した関大、同志社での編入面接では上記の内容を聞かれた記憶があります。今思えば、就活の面接で聞かれた内容に似ています。
注意点として、大学によっては圧迫面接を実施してくることもあります。自分が回答した内容に対して意地悪な質問をぶつけられたり、場合によっては論破されることもあるでしょう。
そういう時は、焦らず冷静に返答することを心がけてください。
面接対策を徹底的に行っていれば、それが自信になって、なにがあっても冷静に対応することができるはずです。
大学編入×究極の面接対策

ここからは筆者が行った編入面接の対策法を解説します。
編入コースで有名な専門学校の講師の方から教わった方法でもありますので、参考にしてください。
1:『将来の目標』と『学部の特徴』を結びつける。
編入は目的ではなく手段の一つです。
目標を達成するための手段の一つが「編入」なので、その目標を叶えるために、この大学で何を学びたいのかを『学部の特徴』に上手く結び付けて話しましょう。
この2つを上手く結びつけるコツは、他の大学とは違うその学部の特徴を3つ見つけ、それを志望理由にすることです。
その学部を志望する理由が3つあれば、なぜその学部でなければならないのかという説得力が増すからです。
例:将来の目標は『高校の英語教師』
教職過程を履修し自身の英語力も向上させ、教員採用試験に合格したい。短大・専門学校では高校教員を目指すことは出来ないので編入を志望する。
志望学部の特徴は、『教員採用試験の合格実績で有名』『英語教育で有名な○○教授がいる』『カリキュラムが充実している』
学部の特徴を見つける方法として、HPを見るでも問題ありませんが、大学の最新パンフレットを1部持っておくと何かと使い勝手が良いです。
『![]() スタディサプリ』を活用すれば、全国の大学の資料請求ができるのでお勧めです。
スタディサプリ』を活用すれば、全国の大学の資料請求ができるのでお勧めです。
2:ストーリー性を持たせる。
これは編入の面接に限らず重要な点ですが、『卒業後の進路を目指すきっかけ』については、一連の流れにストーリー性を持たせて話すほうが良いです。
そうすることで、面接官に伝わりやすくなるからです。
ただの箇条書きを見るよりも、起承転結のある物語の方が記憶に残りやすいですよね。
こちらの記事が参考になると思います。
3:将来の目標は出来る限り明確に。
編入試験に限らず、面接では抽象的なことではなく、より具体的なことを話すのを意識したほうが良いです。
具体的に話したほうが、『志望理由』『将来の目標』『きっかけ』に説得力が生まれるので、面接官の記憶にも残りやすいです。
抽象的なことを話しすぎると、他の受験生と被る確率は高くなりますし、そもそも説得力に欠けます。
面接で話したことを編入後に必ず行わないといけない訳でも無いので、その時点での考えを明確に言語化して面接官るということを心がけてください。
4:本を2冊準備する。
編入試験の面接で『最近なんの本読んだのか?』という質問に答えられなければ最悪なので、最低2冊の本を面接用に準備しておきましょう。(習慣的に読書をしている場合は問題なし。)
志望学部や進路に関する本がベストな選択です。
なぜ2冊なのかというと、1冊は『他には何を読みましたか?』と聞かれた際の予備です。
なので、初めから2冊とも答えるのは極力控えておいたほうが良さそうです。
『本の要約』『印象に残ったこと』『本に対する自分の考え』くらいは最低限準備しておいたほうが良いです。
もし、面接までに2冊も準備できないという方は以下の方法をお勧めします。
- 志望学部系の本を2冊選ぶ
- 本の要約をネットで調べる
- どこかの章だけ真剣に読む(=印象に残った部分)
- 読んだ章を極める(=ネットサーフィン)
- 読んだ章・ネットの要約から自分の考えを言語化する
5:教授を2人準備する。
師事する教授を見受ける作業は、志望理由の説得力を増すためにも非常に大切です。
大学のHP、パンフレットで志望学部が研究領域の教授を2人見つけて、その教授が書いた論文・著書を読んで、ぞれに対する考えをまとめておきましょう。
論文を探すときじゃ以下のサイトが鉄板。
2人準備しておく理由は、『その教授、来年からいなくなるよ』と面接官に返された時の備えです。
面接で重要なポイント


話すときは『結論→理由』
何事も結論から話しましょう。「理由」→「結論」の順番で話すのは何があってもNGです。
結論から話すことは、相手への配慮という意味でビジネスマナーの一つと言えます。どんな人でも相手の話を聞くことに長い時間完全に集中し続けることはできないので、最も伝えたいことを早めに伝えるようにしたほうが、相手に集中して聞いてもらえる可能性が高くなります。
引用:報連相は完結に!結論から話せるようになるためのコツ WORKPORT
「結論」から話すというのはビジネスの世界では当たり前のことです。
「理由からダラダラ話して結局何が言いたいのか分からない」なんてことにならないためにも面接対策と結論から話す癖は大切です。
『結論』は抽象的であっても構わないので、一言で伝えるように意識しましょう。
2:『結論』後の『理由』は具体化。
「結論は抽象的」に、「理由は具体的に」です。
具体的に話すには、志望理由やきっかけを掘り下げていく必要があります。就活で大切な「自己分析」と同じことです。
3:自分の言葉で伝える対策法
緊張して丸暗記した原稿をロボットみたく読んでしまった。。
なんてことにならないように、自分の言葉で話す対策をしておきましょう。
お勧めの対策法は、「話し言葉で書いた原稿を暗記する」というものです。
「と思ったんですね。」「あのー」みたいな言葉を初めから原稿に含んでおくと、丸暗記でも自分の言葉で話している雰囲気が出ます。
自分の言葉であらかじめ文字起こししておくイメージです。
最後に
今回は以上になります。
ちなみに筆者は、この対策法で大学編入の面接にも合格しましたし、第一志望の会社から内定も頂けました。
大切なのは、自分の中で一貫した軸を持っておくことだと思います。そうすることで、どんな質問が飛んできても柔軟に対応することが出来るはずです。
適度な緊張と適度なリラックスが最高のパフォーマンスを引き出すみたいなので、是非参考にしてください。
編入の面接対策で、こちらの書籍は非常にお勧めです。
【スーツ着こなし12か条】最低限守るべきルールで周囲との差をつくる着こなし術。